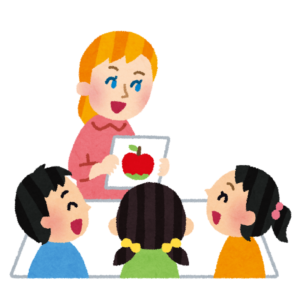
はい、どうも。カワウソだよ。
現在は英語ブームだ。コロナ禍以前は観光客が増加していたし、その影響もあるのだろう。
「英語ができるようになりたい」という人も大勢いるだろう。
しかし、では「英語ができる」とはどういうところだろうか。
もちろんいろんな基準があってしかるべきだろうし、例えば資格試験をとっていなくても英語を喋れる人はしゃべれる。
しかし、そうはいっても試験の得点で考えてしまう人がいる。僕自身その一人だ。
本当はあまりよくないのかもしれないけれど、今回は資格試験の中でも特にわかりやすい基準、例えばTOEICではどのくらいとればいいのか、TOEIC何点以上を取れれば『英語ができる』アピールしてよいのかを考えていこう。
TOEIC『平均以上』は上達とは言えない
まず、TOEICに限らずよく言われるのは、「平均よりはできる」という言葉。
たしかに、平均よりできるというのなら、人並み程度にはできるということだろう。
しかし、平均以上というだけで、英語ができるのをアピールすることはなかなか厳しいだろう。
ちなみに、TOEICの受験者平均点は578.8点。同サイトによれば、慶應義塾大学SFC平均で750、早稲田大学国際教養学部平均で770だ。
多くの場合、TOEICを初めて受験するのは高校卒業後だ。民間試験の導入が検討されたことにより高校生でもTOEICを受験する人が増えたかもしれないけれど、基本は英検だ。また、いくら就職熱心な早慶の学部といえども、1年生の時点で全員がTOEIC対策を熱心にやっているわけではないだろう。
しかしそういう人を含めても、平均が700点後半だ。おそらく対策している人は800とか900点を軽く取っている。
一部ブログの中には、600点や700点を取っただけで「TOEICできます!」とアピールしているものがあるけれど、彼らは、英語を特別に勉強していない一部の大学生よりも点が低いことになる。
もちろんTOEIC600程度でも平均以上ではあるし、そういう人の記事も需要はあるのだろうけれど、できればもう少し上を狙ってほしいところだね。
パレートの法則にならう
『働きアリの法則』で考える
さて、平均点が使えないとすると、いったいどうすればTOEICの基準値を測ることができるだろうか。
そこで使って生きたいのが、パレートの法則という経験則だ。
このパレートの法則、働きアリの法則ともいわれているよ。
で、このパレートの法則はどういうものか説明すると
働きアリの中で、一生懸命に働いているのは2割
たまにさぼっていたり、あるいは常にさぼっているような働きアリが8割を占める。
で、一生懸命な働きアリと、そうでない働きアリの割合は2対8になる。
これがパレートの法則の例だ。
実は、この2:8の法則が、暮らしやビジネスに応用されるってことで、昔流行ったんだ。
例えば、
会社の収益の8割は、労働時間の2割から生み出される
商品の売上の8割は、全体の2割の商品から生み出される
これは、経済に限らない。いろんなところでこの放送は成立する。
例えば、国の人口を多い順に足していくと、
33番目の国を足したところで世界人口の8割に達するよ。
(参照 いろいろ気になるどっとこむ )
世界の国の数は196だから、
33番目ってことは、
33/196= 0.17
つまり、世界の人口の80パーセントは、人口上位17パーセントの国にいるんだ。
ぴったり2割じゃないけど、四捨五入して2割になるね。
このパレートの法則から考えると、上位20%に入っているかいないかで扱いが大きく変わっていくのではないかと思うよ。
上位2割は偏差値60
さて、このパレートの法則で世の中が上位20%と下位80%とに分かれることはわかってくれたかと思う。
で、さらに、上位20%に入ることの重大さを実感してもらうために、ある指標を考えていくよ。
その指標とは、偏差値だ。
計算すると、学力が全体の上位20%の人の偏差値は59。割りきって、60と考えよう。
この偏差値60という基準を超えると、『勉強ができる』という認識になるのではないだろうか。
例えば、河合塾 の発表では、偏差値60がボーダーの大学は
明治大の法学部や名古屋大の工学部などがある。
旧帝大やMARCHレベルということは、社会的な評価は高いよね。
英語の「できる」の基準も、これにならって、「上位2割」としてかんがえよう。
上位2割が取れれば、偏差値60の世界に入ることになるのだから。
「英語ができる人」のTOEIC得点目安は?
上位20%のTOEIC点は750点前後
ほんとは4技能測れるTOEFLの方がいいだろうけど今回はTOEICの点数を英語ができるできないの判断基準とするよ。
なんせ、日本人の受験者数が桁違いだし、
TOEICはTOEFLよりも幅広い英語レベルの人が受けているからね。
以下、TOEICを採用しよう。
第231回 TOEICの統計で、上位20パーセントなのは
リスニング 395~420
リーディング345~370
トータル 695~745
だよ。
つまり、TOEICを基準に「英語ができる」といえるのは、少なくとも750点レベルということだろう。それを超えると、受験者の上位20%、偏差値60を超えていることになる。
実際、例えばオンライン英会話のNative Campでは、TOEICの点数が750点以上だと日本人でも講師になれるチャンスがある。
となると、やはり上位2割、750点程度が、英語で食べていける最低ラインなのではないかと思うよ。
TOEIC730点の壁は正しかった?
ここまで考えてきて、ひとつTOEIC業界のあるあるを思い出した。
TOEIC界隈でよく話される言葉に
730点の壁
というのがあるよ。
まずは、730点を目安にしよう、TOEICを勉強していけば730までは何とかなるけれど、それ以上を目指すには勉強法を変える必要がある、とかそういうものだ。
つまり、TOEIC730まではガムシャラにやっても何とかなる。しかし、それ以上となると、考えながら勉強しないといけない
それが、俗にTOEIC界隈で言われる『730の壁』だよ。
受験でも、偏差値60の壁はあるだろう。大体偏差値60を境に、これ以上の偏差値を取れる人は常勝だし、60に満たない人はなかなか偏差値60を超えることができない。
どうして730なんていう中途半端な数なんだろうと思っていたけれど、偏差値60の壁のことを意味していると考えると納得だよ。
(追記)TOEIC730点の壁は昔な話か
ここまではなした「上位2割=750点前後」というのは、2018年における話だよ。
2020年11月実施のテストを見てみると、上位20%はおよそ800点になっている。
コロナの影響で、英語への意識があまり高くない人の受験が減ったのかもしれないけれど、実際のところは分からない。
受験者の皆さんは、最近のデータを見て判断することをオススメするよ。
TOEIC750の次は895!?
では、TOEICで750を超えている人はどのあたりを目指すべきだろう?
これも同じ、パレートの法則で考えよう。
つまり、20%の20%で上位4%の得点を調べてみよう。
上位4%というのは、上位20%の中でさらに上位20%だ。相対評価で『めちゃくちゃ英語のできる人』と評価されていいだろう。
で、その『めちゃくちゃできる人』の基準値は895。ほぼ900といっていい。
TOEICでは鬼のように900点後半を取る人がわんさかいるけれど、全体で見れば900点以上は4%なんだね。ちょっと安心したよ。
ちなみに、上位4%というのは
偏差値だと67( 東大理I 早稲田政経など)だ。
東大生や早慶上位学部の人からすれば、明治大法学部生を「勉強できる」領域に入れるのに抵抗あるかもしれない。
それと同じで、TOEIC895点取得者から見れば、TOEIC750点なんて大したことないように思うよね。
(追記)上位4%は、985ではなく895点の間違いでした。
この場を借りてお詫びいたします。
でも、偏差値50の人からみたら、明治大法学部は勉強できる方だよね。
同じように、TOEIC750は、英語力が平均的な人からみて
「英語ができる」
範囲にいる
ってことだよ。
纏めると、
平均的感覚からして英語ができるの目安はTOEIC750点。
英語ができる人からしてできる人の目安は895点
今回はここまでだよ。
読んでくれてありがとうだよ(^●ω●^)
コチラもオススメ!
英検とTOEICの難易度を比較する前に洋書を1冊読もう
日本人英会話講師